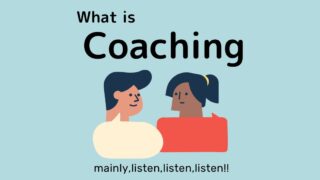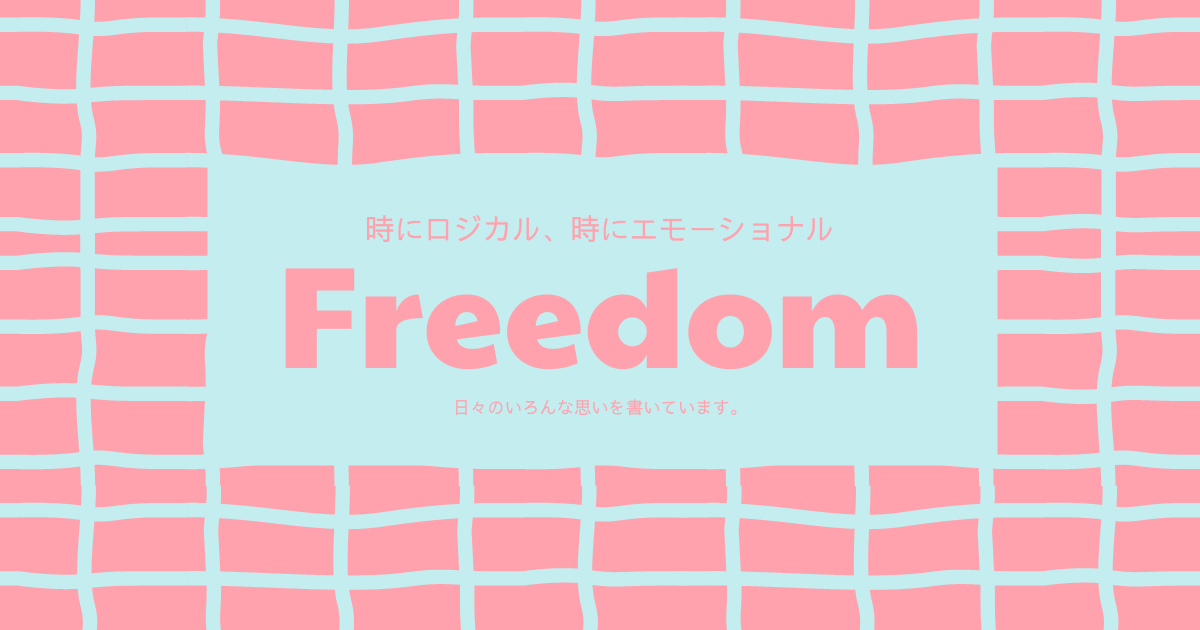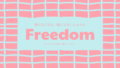こんにちは、いけばなの先生とコーチングのコーチ二足の草鞋修行中のこなつです。
今日は能のお話です。
私は10年程前、ひょんなことから薪能のチケット(めちゃくちゃ良い席だった)をいただいてから、能を観るようになりました。
最近能を観ていなかったのですが、先月、能の聖地、佐渡に行ってきました。
いやー良かった良かった。
今回の演目は井筒。残念ながら雨で屋内の能楽堂での観劇となったので、次回は薪能を観たい!!
この記事では、いけばなに取り組む自分自身を通して感じた能の感想を書きました。
佐渡の能について
先月佐渡に行ってきました。
佐渡は、能の大成者と言われる世阿弥が島流しとなり、晩年を過ごした場所です。
そのためか、佐渡は今でも地元の一般の人たちが能に取り組むという文化が残ってる貴重な場所です。

共感の嵐(芸人だもの)
佐渡の能の何が良いって、“一般人(素人さん?)の能”につきる。
私は、一般人の能を観たのは今回の佐渡が初めてでした。
それまでは、国立能楽堂や有名な薪能会場で高いお金を払って、プロの人の能を観てきました。
どれも素晴らしかったです。
でも、一般の人の能は違う意味で素晴らしい。
観ながらいろいろ思うんですよね、普段の生活の中でどれくらい練習を重ねてきたのかな、とか。
能面って被ったらほとんど何も見えないわけですよね。(前体験コーナーで身に着けた)
能の装束もすごく重いし。(前体験コーナーで身に着けた)
そんな物を身に着けて舞うわけですよ。
シテ方だけでなく、謡の人たちだって、あの板間に何時間も正座をしているんですよね。
想像するだけでも足がしびれてきます。。
演者さんたちが、お勤めや家庭の合間に練習をしている風景を想像するんですね。
もうそれだけでグッときますね。
がんばれがんばれ!!そんな気持ちになります。
きっとそれは、私自身がいけばなを通して、普段の生活の中でああでもないこうでもないと練習を繰り返している、そんなものと重ねているんでしょうね。
楽しいだけの趣味の世界から、本格的に取り組みだして、苦しいこともたくさんあったり、その結果嬉しいこともあったり。そんな経験があるから、舞台を観ながら共感しちゃうんでしょうね。
分野は違えども
和文化に限らず何事も、取り組む分野は違えども、共通することってたくさんあるんですよね。
そんな風に思ったとき、風姿花伝を思い出しました。
風姿花伝は世阿弥が書いた能の指南書です。
今日では、能だけではなく様々な芸事に通じる指南書と言われていて、私もいけばなの座学中によく耳にしました。
結局何事も一生懸命向き合うときに共通することだらけなんだなー。
その風姿花伝には“花”という言葉がたくさん出てきます。
お花の花ではなくて、その人の、その人も持つ芸の魅力?のようなものかな?と思っていますが、難しくて、正直まだよく分かってません、、
少しずつ読み解いていきたいものです。
花の道、芸の道は続く..
To be continued..
演目“井筒”と自己基盤を踏まえた感想は次の記事で書く予定。
お楽しみに~
おススメ能漫画
その昔いただいた薪能チケットの事前学習のために、軽い気持ちで読み始めたらハマった能漫画です。
成田先生の画力のすごいことときたら!
小面の醸し出すいじらしさとか可愛さときたら!